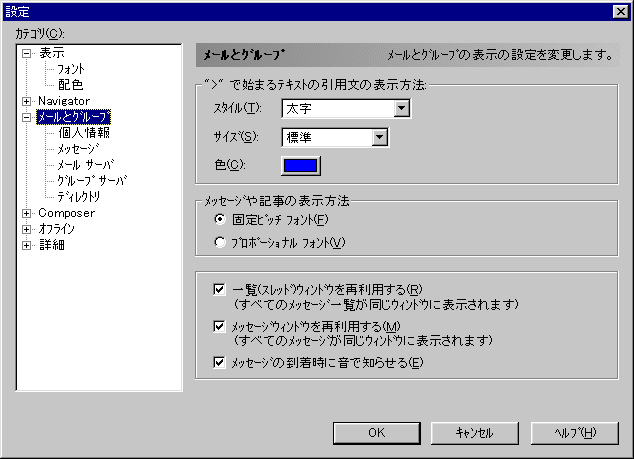
「設定」ダイアログの設定
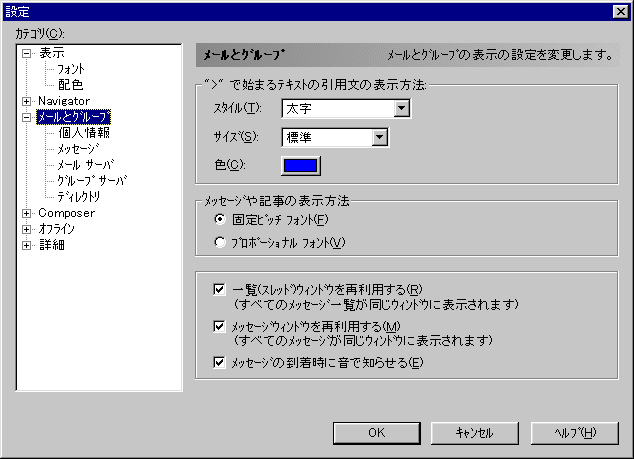
1.「">"で始まるテキストの引用文の表示方法」
多くのメールソフトにはメールを受けとった相手に「返事」を出す時に便利で簡易な「返信メール」という機能があります。
通常メールを出す場合、宛て先(相手のメールアドレス)とタイトルは入力必須です。タイトルはいいにしても、宛て先の入力は大変面倒です。なにしろインターネットメールの宛て先は長いですからね。しかし大抵のメールソフトはアドレス帳を備えていて、そこに登録しておけば、いちいちキーボードから入力しないで済むようには工夫されています。それでもアドレス帳から選択をしなければなりません。
「返信メール」機能は、ある人から来たメールを読んでいる時にメニューなりボタンから「差出人へ」というのを選ぶと、宛て先にはその相手のメールアドレスが、タイトルには、その人のからのメールのタイトルに「RE:」というものを冠したタイトルを自動的に付けてくれて、後は本文を書くだけでいいようにしてくれます。大変便利な機能で文通的なやり取りには欠かせないものです。
その時に更に相手の文章を引用するということをよく行います。手紙には電話と違って大きなタイムラグがありますから、出した本人もどのような内容を出したかは覚えていません。またいくつかの話題が含まれるのが普通ですから、返事を出す側が相手からの質問や話題に対して書いても、何をいっているのか分からない場面が多々あります。
そこで相手の文章をちょこちょこと引用することで話しの流れを作り出す訳です。丁度電話で話しているような効果を醸し出すことができます。 これが電子メールのもつ、普通の手紙にはない一つの流儀であると理解して下さい。
で、前置きが長くなりましたが、その引用をした文章とそうでない文章を区別するために、今までも流儀として「引用文」には通常、行の先頭に「>」という文字を冠します。そしてこのように「>」で始まった引用文をよりはっきりと他の部分と区別できるよう大きさや色などを変更できるというのがここの設定です。
ここは完全に個人の好みなので、自分で好きなように設定するといいでしょう。あくまで自分がメールを読むときの状態に過ぎず、何ら送信メールなどに影響を与えるものではありません。
2.「メッセージや記事の表示方法」
ここもあくまで表示の方法です。「固定ピッチフォント」というのは、全ての文字が同じ幅のものです。一方「プロポーショナルフォント」というのは、文字によって幅を変えてあり、名前の通りちょっとカッコよく見えるフォントです。たとえば、「i」と「M」を同じ幅で表示すると、「i」は間延びした感じに見え、「M」は狭苦しい感じに見えます。そこで文字によってダイナミックに幅を変え、見栄えをよくしています。
しかしプロポーショナルフォントには大きなデメリットがあります。メールでは基本的には文字しか送れないので、よく文字で絵を描いたりします。また「|」や「−」を使って表を描いたりもします。このような時固定ピッチでないため、意図したように表示できない場合があります。表などは列ががたがたになってしまい、絵などは不格好になる可能性があります。「固定ピッチフォント」は確かにプロポーショナルではないですが、それほど見苦しい訳でもないので、こちらを推奨します。
これより下の設定は特に気にする必要はありません。デフォルトのままチェックしておいて構いません。
ここには送受信に関わる事項もありますが、基本的に表示上の項目です。しかし送信相手に見られるものですから、まじめに記述しましょう。
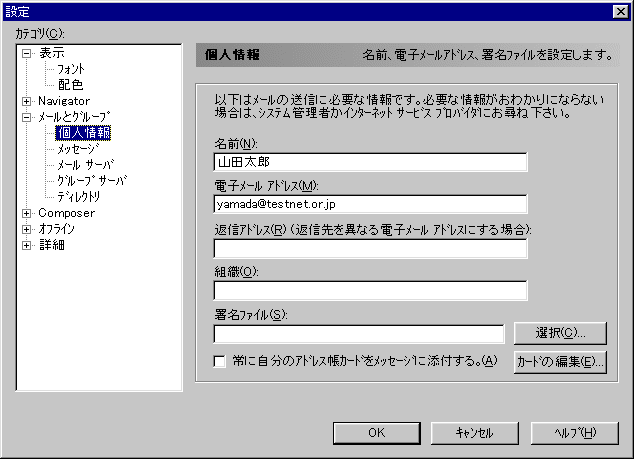
1.「名前(N)」
ここは普通にあなたの名前を記述します。受け取った側の「差し出し人」欄に表示されるようになります。日本語(漢字)を使ってもかまいません。
2.「電子メールアドレス(M)」
メールアカウント@サーバドメイン名という形式の自分のメールアドレスを正確に記述します。これを間違えると返信メールが帰ってこなくなります。
3.「返信アドレス(R)」
メールを出した相手からの返信を受ける場合に、特に上記の電子メールアドレスとは違うアカウントに受けたい場合に指定します。形式は同じくメールアカウント@サーバドメイン名になります。相手が返信メールを送った場合、こちらのアドレスにくるようになります。やはり間違えると返信メールが帰ってこなくなります。
特に別にアカウントがない場合は記述する必要はありません。その場合は上記の電子メールアドレスがそのまま利用されるだけです。
4.「組織(O)」
個人の場合に特に記述する必要はありません。
5.「署名ファイル(S)」
「署名」なんてものを今更説明はいらないと思いますが、署名をファイルに書いておき、そのファイルをここで指定します。
署名の形式ですが、名前とE-mailアドレス、ホームページがあればそのアドレスを書くくらいが一般的です。よく住所や電話番号まで書く人がいますが、あまり好ましくありません。昔通信環境があまり整っていなかった頃は、少しでも送信量を減らすために、署名は4行までという暗黙の決まりもあったくらいです。今はそれ程うるさいことを言う人もいませんが、あまり派手な署名は避けましょう。
次のカードに関する部分は無視してください。設定しない方がいいです。
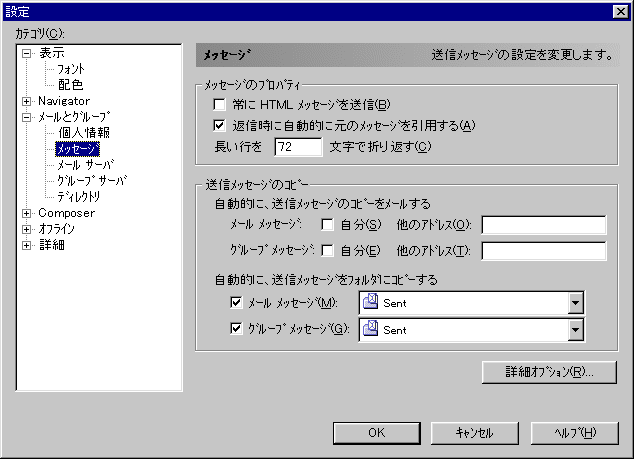
1.「常にHTMLメッセージを送信(B)」
ここは絶対にチェックしないで下さい。「HTML形式」では受け取る人によっては読むことができません。将来的にはこれが当たり前になると思いますが、まだ時期尚早です。因みにHTMLとはHyper Text Markup Language の頭文字です。
2.「返信時に自動的に元のメッセージを引用する(A)」
先ほど引用の話をしました。あの趣旨からするとここはチェックしておくべきでしょう。チェックすると全文が引用されますが、不要な部分は削除すればいいだけなので不都合はないはずです。
3.「長い行を[ ]文字で折り返す(C)」
これはデフォルトの「72行」くらいにしておきましょう。要は行があまり長いと読みにくいので、強制的に折り返してしまおうということです。
4.「自動的に、送信メッセージのコピーをメールする」
これはチェックする必要はないでしょう。
5.「自動的に、送信メッセージをフォルダにコピーする」
これは言葉の通り送信したメールを指定フォルダにそのコピーを保存していおくかどうかを決めるものです。これはチェックしておいた方がいいと思います。こうしておけば自分がいつだれにどんなメールを出したのかが、後で確認することができます。フォルダはデフォルトのまま「Sent」でも構わないと思います。
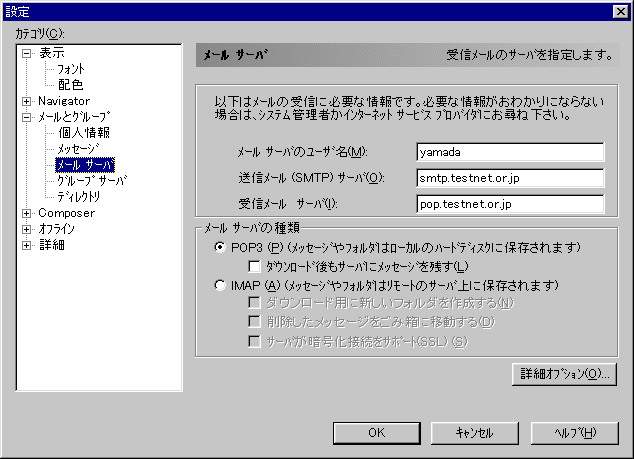
1.「メールサーバのユーザ名(M)」
通常は「メールアカウント」と同じ意味です。書類などには「POP3アカウント」と書かれている場合もあるでしょう。「メールアカウント」とは普通はメールアドレスの「前半部分(@の前)」ですが、たまに違う場合もあるので気を付けましょう。また多くの場合、プロバイダの「ユーザID」とも同じはずなので、特に「アカウント」というものが記述されていない場合は「ユーザID」と同じものを指定してください。
2.「送信メール(SMTP)サーバ(O)」
送信用のサーバ(SMTPサーバ)のサーバ名を記述します。
SMTPとは、Simple Mail Transport Protocol の頭文字です。
メールサーバには送信用と後述する受信用のサーバがあります。ただしプロバイダによっては双方に同じサーバを使っており、メールサーバとしか書類に書いてない場合もあるでしょう。その場合はそのサーバ名を双方に記述すればいいだけです。
3.「受信メールサーバ(I)」
受信用のサーバ(POP3サーバ)のサーバ名を記述します。
また受信サーバはPOPサーバと書いてある場合もあるので、気をつけましょう。
4.「メールサーバの種類」
ここはデフォルトの「POP3(P)」のままでいいです。
「ダウンロード後もメッセージをサーバに残す(L)」もチェックする必要はないでしょう。
5.「詳細オプション(0)...」
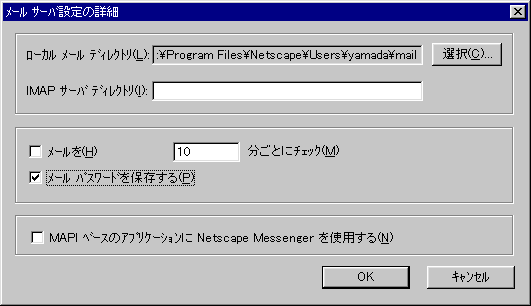
1.「ローカルメールディレクトリ(L)」
デフォルトのままでいいと思います。
2.「IMAPメールディレクトリ(I)」
空欄のままでいいです。
3.「メールを(H) [ ]分ごとにチェック(M)」
ここもダイアルアップの人はに基本的に関係ありません。
4.「メールパスワードを保存する(P)」
ここはチェックしておいたほうがいいでしょう。さもないとアクセスの度にパスワードを入力するはめになります。
このパスワードとは「メールサーバ」へのパスワードです。多くの場合はプロバイダにダイアルアップする時のパスワードと同じですが、時折違うものを指定させるプロバイダもあるので気を付けましょう。特にプロバイダへのユーザIDと「メールアカウント」が違っているような場合は、パスワードも違う場合が多いようです。POP3パスワードとか、メールアカウントパスワードなるものがあったら、そちらの方だと思います。